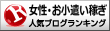スポンサーリンク
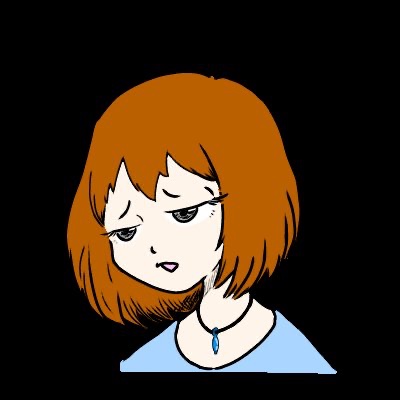
離婚後に必要な手続きは、子どもがいる場合、さらに必要になります。
漏れがないようにチェックしておきましょう。
- 子どもに関する手続きにはどのようなものがあるのか
- 手続きはどこで行えばよいのか
- 必要書類はどのようなものがあるのか
スポンサーリンク
目次
姓や戸籍の変更

普通は離婚すると旧姓に戻ります。
母親が旧姓に戻すか戻さないかで手続きの仕方が変わってきます。
母親が旧姓に戻す場合
子どもがいる夫婦が離婚し、旧姓に戻った母親が親権者となった場合、子どもの姓や戸籍は何も手続きをしなければそのままになります。
したがって、旧姓に戻った親権者が子供にも同じ姓を名乗らせたい場合や同じ戸籍に入れる場合は以下の手続きが必要になります。
子の氏変更許可の申し立て
子どもの姓を親権者の姓と同じものにしたい場合、子の氏変更許可の申し立てを行います。
手続きは家庭裁判所で行うことになります。
- 子供の戸籍全部事項証明書
- 両親の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
- 収入印紙800円分
- 連絡用郵便切手(裁判所により金額が異なる)
- 届出人の印鑑
母親が旧姓に戻さない場合
この場合、妻が「離婚の際に称していた氏を称する届」を出し、手続きした後、「子の氏変更」の手続きを行います。
なお、「子の氏変更」というと、子供の姓を変える手続きと勘違いしてしまうことがありますが、子供の戸籍だけを変える場合にも「子の氏変更」になります。
子どもの戸籍を母親側に入れる
①家庭裁判所に申立て
子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
申立書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
- 子の氏の変更許可申立書
- 子どもが入っている父親側の戸籍謄本と母親の戸籍謄本(どちらも離婚の記載があるもの)
- 収入印紙(子供1人につき800円)
- 郵便切手(即日交付を受ける場合には不要)
申立書は直接家庭裁判所に持参する以外に、郵送で提出することも可能です。
裁判所によっては、直接申立書を持参すれば、即日許可がおり、その場で審判書の交付が受けられるところもあります。
②審判書の受け取り
申立書に不備等がなければ、すぐに審判書が交付されます。
即日交付の場合にはその場で審判書を受け取れ、郵送の場合には、後日家庭裁判所から審判書が送られます。
子どもを自分の籍に入れる手続き
子どもを自分の籍に入れる場合は、各市区町村の役所の戸籍課で手続ができます。
- 子の氏変更許可審判書謄本
- 入籍届
- 子の戸籍全部事項証明書
- 入籍する親の戸籍全部事項証明書
- 届出人の印鑑
児童扶養手当の申請

子どもが18歳の誕生日後の最初の3月31日まで日数があり、以下の条件を満たす場合、役所の子育て支援課(児童課など)で申請をすれば、児童扶養手当の受給資格が認められます。
- 両親が離婚
- 両親が死亡した
- 両親のうち一方が一定以上の障害レベルになること
- 両親のうち一方がDV保護命令を受けている など
- 子どもの入籍届出後の戸籍謄本
- 住民票の写し
- 申請者名義の預金通帳(振込口座のわかるもの)
- 申請者の所得証明書
児童扶養手当は収入に応じた経済的支援を受けられるもので、所得制限があります。
児童手当の受取人変更

児童手当は中学生までの子供を育てている保護者に支給される手当です。したがって、対象となる子供を育てていれば離婚していなくても支給されます。
そのため離婚前後で受給権者が変わる場合は児童手当の受給者を変更しなければなりません。
住民票のある市区町村で新しい受給権者が申請をします。
- 元の児童手当受給者が受給事由消滅書を提出
- 新しい児童手当受給者が認定請求書を提出
- 認定請求書
- 受給者名義の通帳、キャッシュカードなど
- 受給者の健康保険証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
学資保険などの受取人変更

学資保険の契約者と受取人が配偶者である場合、離婚後に契約者と受取人を親権者に変更しましょう。
もしそのままにしておくと、勝手に学資保険を解約される可能性もあります。
学校の住所変更
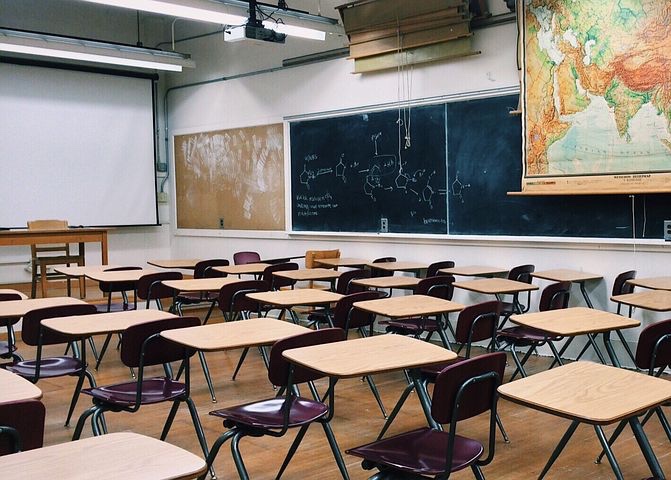
公立小中学校の場合、住所変更は市区町村役所で行います。
また、子供名義の銀行口座から給食費や学費を引き落とししている場合は、子供の銀行口座の名義変更をすると同時に学校への連絡も忘れずに行いましょう。
まとめ
離婚時は婚姻時より、複雑で多くの手続きが必要になります。
チェックリストなどを作成し、漏れのないよう手続きを行いましょう。
↓ランキングに参加しています。クリックしていただけると嬉しいです
スポンサーリンク