スポンサーリンク
2019年12月23日に新しい養育費算定表が、裁判所のウエブサイトで公開されました。
今回の改定によって、全体的に養育費が上がったように見えますが、実際良いことばかりなのでしょうか。
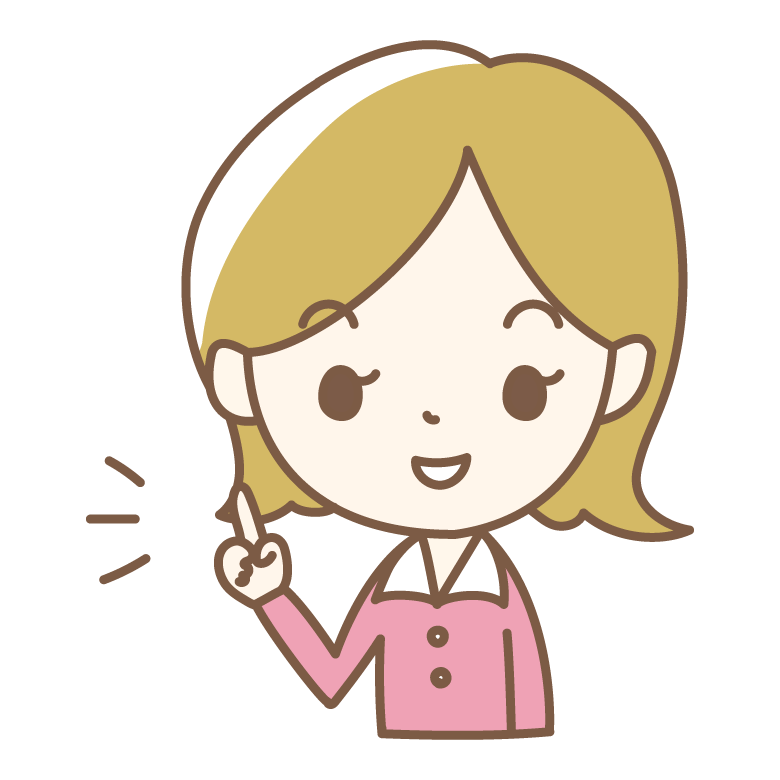
ここでは、養育費算定表の変更点と、そのメリット・デメリットを紹介します。
- 養育費算定表がどう変更されたのか
- 新養育費算定表が決められた背景
- 18歳成人への対応
スポンサーリンク
目次
養育費算定表の変更点

今回の養育費算定表の改定は16年ぶりになります。
全体的に増額されるか、条件によっては金額が変わらないかのどちらかで、減るケースはないようです。
例えば0~14歳の子ども1人を育てる親の年収が300万円
相手の年収が500万円の場合
≪月額養育費≫
旧 2~4万円
↓
新 4~6万円
養育費はどのように決めるのか?

算定表では、総収入から税金や住宅費などの必要経費を差し引いた「基礎収入」を夫婦それぞれで算出し、それを基に子どもの生活費をどう分担するか、という考え方で決めています。
この16年の間、所得税などの税率の変化、公立校の学費の減少など、現在の生活形態も変化してきて、これまでの算定表では合わなくなってきていました。
このような点も考慮して見直した結果、今回の養育費の増加傾向になりました。
養育費算定表の改定によるメリット・デメリットはあるのか
一見、増加傾向である養育費ですが、受け取る側からすればメリットがあるように見受けられますが…
そもそも「メリット・デメリット」ということを考えるものでもないのかもしれません。
元々、養育費の水準は低いと言われてきました。今回の改定で、現在の生活形態に見合った額を算出してくれたのはよかったとは言えるでしょう。
18歳成人への対応
令和4年4月に、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
それに合わせて養育費も18歳までになってしまうのでしょうか?
裁判所の報告書では「大半の子どもは18歳の段階では経済的に自立していない」として「現行通り20歳まで養育費を支払うべき」としています。
まとめ
今回の養育費算定表の改定では、生活水準の見直しで全体的に増加傾向ではありましたが、きちんと支払わなけば意味がありません。
子どもの生活水準がきちんと確保できるように、養育費の未払いがないような制度を期待したいものです。
↓ランキングに参加しています。クリックしていただけると嬉しいです。
スポンサーリンク




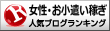
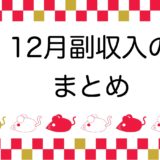
】動画アフィリエイトできるアプリ-160x160.png)